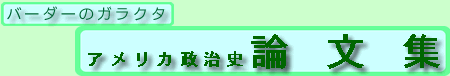
(昭和47年12月執筆) アメリカの自然保護、終章 まとめ
終章 まとめ
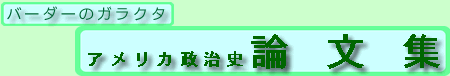
(昭和47年12月執筆) アメリカの自然保護、終章 まとめ
終章 まとめ
「宇宙船地球号」が世界中で認識され、将来の資源の枯渇が明らかとなった今日、社会主義国であっても資本主義国であっても同じように何らかの自然保護政策をとらねばならないだろう。地球の大気、土壌、資源、動植物を保護し、保存することは今や人類生存の最低条件となっているからである。しかし、自然保護を政策として推進していくには、私的利潤追求が中心の資本主義国よりは社会主義国の方が統制がとりやすいのではないかと考えることができる。そこで、まず、社会・共産主義国と資本主義国とを比較してみよう。
ソ連の自然保護の文献を見ると、アメリカなど先進資本主義国がもたらした過度の汚染・自然破壊などを巧みに例証し、マルクス・レーニンによる自然保護の主張を引用してソ連がいかに自然保護に留意し、実践しているかという点が細かに書かれているが、アメリカなどの先例があるにもかかわらず、ソ連もいかに豊富な自然を破壊してきたかという点には当然ながらほとんど全くふれていない。しかし、ソ連における公害の事実、バイカル湖付近の貴重な自然の破壊、シベリアにおける毛皮獣の濫獲などは明らかであり、保護上有効な規制などがとられた年代を米国と比較すると、決して先取りしていると言えないばかりでなく、かえってアメリカの後を追っているようなところも見られる。
これは、今日までの国際社会において、社会主義国といえども単に一般人民の福祉と平等を目的としてくることができず、資本主義諸国との力関係においてほぼ対等であることを大前提として政治を行っていたからではないだろうか。
その政治システムを見れば明らかに社会主義・共産主義をとる諸国の方が、資本主義・自由主義をとる諸国に比して自然の破壊の防止についての規制・政策を行いやすいし、効果的に行われていたなら、今日のソ連邦に於いては公害現象はある程度抑制され破壊も最小限にとどまっていたであろう。
しかし、冷戦状態にあったソヴィエトはアメリカに匹敵し、それをしのぐほどの国力を充実させる必要があった。軍備を整えるために産業も整備され、重化学工業に力が入れられた。内政問題でも、直接国民に害がおよぶわけでもない自然資源の濫獲は国家の力によって強引に推し進められた。革命前にピョートル大帝によって大規模に確保されていた自然も、革命後になると自然は理論上においてのみ保護されていて、実際は保護や破壊に対して何らの興味も示されるところがなかった。マルクスやレーニンが自然の大切さについてどんなに素晴らしい言葉を残していようと、彼らの目指す体制の国家を維持していくためには豊富なエネルギー源を無視するわけにはいかなかったのである。
資本主義国において、自然の破壊がある程度進展し、自らの生命に危険が訪れたときにはじめて事の重大さに気付き、失ったものをとり戻そうとする動きを見せるのは、残念なことだが私的利潤追求による国家の経済的成長、市場の獲得を主眼に資本主義の健全な発展を志向する以上、まあやむを得ないことであろう。しかし、ここで無視することができないのは、社会・共産主義諸国も自己の現状地位を守るために、ある程度の経済発展、工業化を志向しなくてはならないという国際社会の現状である。
一般に、私は思うのだが、社会・共産主義諸国も純然たる人民民主主義を志向し、国民の福祉を念頭に置いて国政を進めていくのならば、産業の発展過程において公害問題、自然破壊はある程度管理されていくはずである。けれども社会主義諸国も私的利益の追求はなくとも公的利益(国家)を追求しなければならない場合には(特に資本主義と相対するような場合には)「追いつけ・追い越せ的」国益追求に進むこととなり、公害の放任につながる危険性をもっているのである。
その点中国はソ連とはいくらか異なる。東洋的自然観をもっており、自然環境との調和の仕組みを重く見る思想がある上に「ぎりぎりのどん詰まりから出発し、もちあわせの資源を使って国造りをしていかなければならなかった中国の特殊な条件に基づいていて、これが期せずして公害対策になった」(京都大学山田慶児助教授)ので徹底して廃棄物の再利用を図っている。中国の場合、資本主義国と張り合う立場にはないが、ソ連と摩擦的関係にある。しかし、国力の差は当初から明らかであり、工業化もかなり遅れてスタートすることになった。いわばソ連の先進国的地位と比較すると、中国は発展途上国的要素が多くあるのである。
社会主義・共産主義諸国とはいっても公害問題の特に深刻なのは今のところソ連が飛び抜けている。それは先に述べたような対米冷戦態勢の経験の結果である。
先に資本主義国において自然破壊がある程度進展し、自らの生命に危険が訪れるまで放置しておくことはやむを得ないと書いたが、社会共産主義諸国の場合は先見の明があるというのではなくこれは政治体制が異なっていても共通する問題である。ソ連においても、自然破壊が自分の首を絞めていることに気付くまでは平気であった。要するに地球上の人類が皆、自然は無限にあり、利用したいだけ利用できると考えていたのであるから仕方のないことなのである。
いや、仕方のないことではない。資本主義国も社会主義国も社会の福祉に充分気を配り、研究に研究を重ねることを惜しまなかったなら絶対に防止できたはずである。要するに国家がどういう姿勢で国際社会の中で自国民の福祉を図ってきたか、その義務が問われるのである。その結果、今の地球上の先進国はどれも国の利益を重視し、(または、個人の利益を尊重するあまり全体の福祉を忘れ)人間としての国民の真の平和・福祉・幸福は考えていなかったということが明らかになる。
それではそのことに気付いた今後はどうなるのかというと、国家は汚染の軽減のためにどれだけ早くどれほどの効果を上げうる政策をとりうるかにかかっていくのではないだろうか。そうなると国家の意思統一がしやすい体制のソ連などの国々がずっと有利になる。クレムリンの意識が自然保護に傾けばソ連邦全体はアメリカなど資本主義国と比較すると、ずっとスムーズに保護主義をとることができる。
それならこれからの自然保護主義時代になると、資本主義は汚染対策などにもたついているうちに、社会主義国に主導権をとられる恐れが出てくるのだろうか。私は否と言いたい。なぜなら、確かに資本主義国では国家の意思決定に人民が乗り気でなく、自己の利益ばかりを考えているということがおこるが、人民のための福祉を真に優先する国家のとりうる規制が強化され、自然保護主義の志向が自己の利益となると自覚した時点で立場は逆転し、汚染防止の技術開発など、自然保護主義を志向する中で自己の最大利潤を上げる方向へ進むことになるからである。特に汚染の防止や既に汚染した化学物質などを回収するための技術は自由競争の主義の中だけにおいて(この場合勿論国家の援助を背景にしていた場合)発明などによる開発のスピードも社会主義諸国よりは速くなれる可能性をもっている。
これからの世界において、地球の管理を考えた場合、地球運営に必要な技術なり理論なりは相互に交換しあい、社会・共産主義国も資本主義国も体制の差を超えて自然保護主義のもとに互いに自国の真の福祉と平和に努力していくべきではなかろうか。そういう意味から、1972年国連人間環境会議にソ連などが参加しなかったことは誠に残念なことである。
今日の自然保護主義のきっかけになり、基調に流れている理論は生態学である。これまでの、大気などの自然資源は無限であるという前提に発展してきた経済(economy)はこれから、資源は有限であるという生態学(ecology)的考え方を重視し、大きく修正される必要があるだろう。
国連人間環境会議で世界に残された原生地域をすぐに隔離し、原始自然に人為を入れないで残そうという決議がなされたのは、この生態学の研究に必要な、本来の自然形成員の相互関係を知る材料として確保するためである。人間など地球上の動物、植物、大気、水などはそれぞれ定まったルールで一定の役割をもって自然を形成しているということはわかっても、更にそれではどれとどれがどのような関係になっているかということは、ごくごく一部分しか判っておらず、今後の研究に原始自然を確保することは必要なのである。
しかし、今日のような特に日本における生態学ブームは一つ間違うと非常に危険なものになる可能性がある。日本人の性格として、本論でもふれたように「御上」とか「あちら」のことに非常に弱く、ある面では自主性独立性がかなり欠けているという特徴をもっているが、この生態学の場合も正にそれでエコロジーという「あちら」の言葉が入ってくると神様のように崇拝し、全てがその横文字で解決される(または、された)と思いこんでしまう。その結果何でもかんでもエコロジーエコロジーである。農薬がまずければ天敵を使い、汚水処理場でもバクテリア使用の分解をもっと広範囲に積極的に取り入れよ、などが叫ばれる。けれども、自然とは人間にとって一体何なのであるか、何のために自然保護をするのかという根本的問いかけがなされていないのである。人間として真に生きる道は何なのであろうかということを考え、自然との関係を認識した上で生態学の意義をつかむのなら良いが、単に生態学を公害救済の学問としてとりあげることは適当ではない。日本という独自の歴史・特性を持つ地域が、自分に最もよくあった自然保護の道を自ら築いていき、自然保護の大原則を作り上げた上で生態学なり何なりの理論を活用すべきだということである。
自然保護の原則のない日本に限らず、それをもっているヨーロッパやアメリカでも生態学を単に定量的な技術の学問としてとらえ、生物の個体数などの関係から生物相互の間の一法則をつかみだそうとしているが、たとえここで一つの法則が見つけだされたとしても、それはあくまでもある特殊な動物や植物相互の間においてのみ成立する事実であり、それをただちに人間に有利な方法で利用していくことは生物として本当に正しいことなのかどうかは疑わしいのである。ここに生態学を今日の環境問題にあてはめる理論としての限界があるのである。私は生態学を否定するものではない。しかし、生態学はあくまでも生物の中のある特殊な場合を研究する学問であるので、生態学の扱いうる分野は限定されているはずだと思うのである。
なぜなら、自然界において、恒常的なバランスというものは存在せず、常に進化を繰り返しているからである。生態学はそうした進化の中の一時期における生物相互のいわば横の関係を示すものであり、時の流れ、生物の歴史性といった無限に延びる時系列のいわば縦の位置にある進化の部門は扱うことができていないのである。今日、世界的に生態学が注目されているものの研究が追いつかないため、「できるところから」汚染解消などに利用されてはいるが、これが理想のパターンであるとして永久に地球運営にあてはめていくことは生物の進化を無視するものである。人類自体が進化を制御したりコントロールしたりできるほど生物学的な力を持っていないのであるから、今日の「自然保護」の感覚で将来もやっていくことは早晩不可能になるであろう。
例えば、自然をまもれという声が高くなり、一つの湖を保護することにした場合、一体どのような方法でその湖を「保護」したらよいのだろうか。というのは、湖は時がたつに従って次第に沼となり湿地となって、最後には乾いた土地になっていくのであるが、今日の湖を将来も変わらずに今日の湖であるように保護していくことは明らかに自然の歴史から見てそれに逆行するものなのである。真の意味で自然の状態においておきたいのなら「保護」とは放っておくことになるのではなかろうか。
また、ある高山の雷鳥を保護することにしたとする。雷鳥は氷河時代の生き残りであり、その生物的寿命はほとんど無いのであるが、ここで人間が保護し雷鳥を絶滅から救ってやることは、雷鳥自身また人間という生物にとって真に意義のあることであるかどうかは疑わしい。地球上に生物が出現したときから今日まで、ありとあらゆる生物が誕生し絶滅してきた。だから生物的寿命を迎えている雷鳥などは進化論的にはあと何百年も生存する必要もないのではなかろうか。
だから、今日人間が「保護」という名のものに生物の進化を無視して現状を凍結することは好ましくないのではないだろうか。
今日自然破壊により、人類が存亡をかけた問題を負うことになったことも極論をすれば人間の生物的存在の限界が来たとも言えるかもしれない。しかし、人間は高度の頭脳をもっている。文化ももっている。もしかしたら、自然を管理することができるように科学が発達することも可能かもしれない。だがこの現在に人間が破壊に対してなしうるのは生態学応用の「保護」なのだろうか。進化論とのかねあいにおいて「保護」することとは一体何を意味するのであろうか。
あまりに話が大きくなったので具体的な現状に戻して考えてみよう。この論文でずっと見てきたように、地球上にはそれぞれの地域に応じた自然保護の行政がとられてきた。はじめはただ失われゆく自然美へのノスタルジアから出た自然保護であったが、人間の活動範囲がより拡大し、科学技術がより進歩することによる、より贅沢な暮らしができるようになると、人間の自然利用は著しくなり、国際的に残された資源としての自然を確保していこうという「自然保護主義」が生まれることになった。そうすると、地球の残された資源をいかに管理していくかという技術的な方法論が各国でなされ、従来からアメリカのとっていたConservationという科学的管理方法が最も有望視されるようになってきた。
これからの自然保護とは、人間が利用するための資源を与えるための、それを有効に使用するための方策なのであろうか、もしそうならば、各国の自然保護行政の独自性は将来消滅し、ただ一つの国際資源保護主義に統一されることになろう。果たして本当にそれで良いのであろうか。
アメリカの自然保護もヨーロッパの自然保護も日本の自然保護もその論理は今後非常に科学的な明解なもので貫かれることになるだろう。保護をするに科学技術をもってすることは実際的政治の上では必然的なものであり、そうあるべきことであるが政治的技術の保護行政に流されてしまいがちな自然保護の論理の背後にある精神的心情的なもの、即ち人間の本能のようなものを無視することは人間の真の生きるべき将来を形成することにはならないのではないだろうか。
身近な美しい自然が失われていくのを嘆いた文化人の自然保護運動はただ当時の人の科学的無知を示すものではなく、今日の保護行政に忘れられている保護の本質的なものを示しているのではないだろうか。そして、この保護の本質的なものは、たとえその国の保護行政がどういう独自な形をもって現れても、生物としての人間は皆同じものであるのと同様に、万人共通のものなのではないだろうか。
最後にジャン・ドルストが「自然が亡びるまで」の中で書いた言葉を引いてこの「アメリカの自然保護」を閉じようと思う。「自然は、人間のために、人間の必要のために保護されるべきではなく、自然が素晴らしいからだ!」
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*