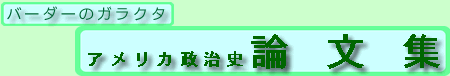
(昭和47年12月執筆) アメリカの自然保護、
第一章 欧米的自然観と日本的自然観、第一節 欧米と日本
二、宗教的背景
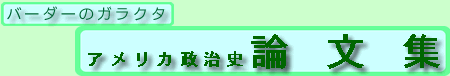
(昭和47年12月執筆) アメリカの自然保護、
第一章 欧米的自然観と日本的自然観、第一節 欧米と日本
二、宗教的背景
古代においては、ヨーロッパもアジアも殆ど同じような宗教に基づいて生活していた。すなわち、呪術的行為によって日常の生活すべてを営んだり、シャーマニズム、アニミズムのように、自然に対する考え方も、人間・精霊・神々の混沌としてとらえていたことなどである。当時の人間は環境に依存して自然の与える恩恵にすがって生活しなければならなかったからである。
しかし、人類の精神史における重要なエポックとなったB.C.15世紀からB.C.6世紀前後にわたる一連の「知的革命」(キャロル・クィグレイ)以後両者は互いにその思想に変化があらわれてきた。
ジョージタウン大学教授のキャロル・クィグレイはヨーロッパ人の自然観の起源を特にヘブライ人とユダヤ人の思想変化にスポットを当てて説明している。
彼はまずヘブライ人の間に生じてきた神に対する新しい観念に注目した。その第一段階はB.C.1400年からB.C.600年頃までの「神託一神論」である。それは、創造主なる神は特別な創造活動の結果として人間をつくりあげ、人間を外におき、他の生物をしのぐ力を人間に与え、自然とその生産物を自分の目的に用いることを命じたというものであった。従って、正統的ヘブライ人は、人間は自然の外にあり、自然と対立しさえするものだと考えるようになっていた。が、しかしこれは神が自然をつかさどっている以上、人間が自然に対して何でも好きなことをして良いとは思ってもみなかった。
けれどもB.C.600年以後になると、ヘブライの教父達は第二の段階と言える「超越的一神論者」となっていた。彼らは、神が自然や時間空間から超越したところに存在することを説いた。この考えは、神が自然の外にあって殆ど自然によって妨害を受けないのならば、神と同じような精神的存在であり、従って自然の外にある人間もまた、自然の法則を学ぶことによってその主人となれるはずであるということを内面にもっているものであった。そしてこの考え方は、実際は大部分の人が依然として神を単に神託的と考えていたので、その時代には反映されなかったが、後にギリシァ人がその意味をつかみ発展させていく。これがギリシァの二元論といわれるものである。
ギリシァ哲学の完成者であるアリストテレスの論理学はきわめて明快なものであったがそれは人間の経験を対立の概念でとらえようとしたものだった。はじめは「生ある」「生なき」、「神聖である」「神聖でない」、「自然の中にある」「自然の外にある」のどちらかであったものも次第にその対立概念を変化させていき、ついには「生」「死」、「物質的」「精神的」、「肉体」「精神」、「人間」「自然」というところまでにいたった。
人間の経験を完全に二つの対立したものとしての概念でとらえることはできないにもかかわらず、この考え方はギリシァ文化の中に組み込まれて広められ、今日まで尾をひいている。
このように、西欧的認識は二元論の上に立っていたので、キリスト教徒もギリシァ論理学の枠組みを通してキリスト教的忠誠心を身につけていった。けれども、西欧社会が以後ずっと二元論の上に立ち続けたわけではない。中世のスコラ哲学においてこの傾向は、一時的に無くなった。それは、虫ケラから神に至るまですべてのものが連続した多様な階層をもつピラミッドを形成していて、そのピラミッドの中には悪は無くすべてのものが善であるというものであった。自然や人間の肉体はたとえ神や霊魂よりは劣っても至上善の神が造ったものであるから善であるとしたのである。だから、かの聖フランシスコが小鳥たちに説教をしたという話が残っているのも不思議ではない。
しかし、それは長続きせず、1400年頃からのルネサンスにより、保守的神学が二元論を含むギリシァ文化の再評価と共に復活した。これにより中世のピラミッド的階層的均衡は大きく崩れ、俗世の長たる国王と聖なる法皇との二筋の支配者によって世界は治められることになった。以上のような流れが近世から近代にかけての合理主義的思想へと受け継がれるに至って、自然はますます人間とは対立していくものとなっていった。
ヨーロッパ的自然観が完全に人間と自然とを対比させるものであって、アジアのはそうではないと断言することはできない。いや、それどころか、思想史の一つ一つに詳細にあたっていったとするなら、かえってそうした傾向がごく一部のものとなるかもしれない。けれども対自然観の主流の中でも主な考え方を拾ってみた場合に、概して今までに述べてきたようなことが言えるといっても、大きな誤りとなることは無いように思われる。私はそういう考え方で、さらに議論をすすめていきたいと思う。
さて、一方アジアでは、中国において、孔子・孟子にはじまる諸子百家の思想の中に、無為自然を説く老・荘や陰陽五行説を説く陰陽家などのように人為を否定し、自然に帰ることをすすめたり、人為自然すべての事象を自然の法則によって説明しようとするなど、自然に昔ながらの敬意を示す思想が続いていた。また、インドにおいてはバラモン教が、梵我一如即ち宇宙最高の原理であるブラーフマン(大我)と個人のうちにあるアートマン(自我)とが全く同一であることを自覚すること---自然の普遍性と輪廻による自我の普遍性の一致---を説いたりしていたが、何といっても今日まで大きな影響を与えることになったのはインドにおける仏教の誕生であろう。仏教は宇宙や人間を造り出した唯一神や人格神を認めないので超越的な存在のみ善とする考えはないこと、また、人間の理性を尊重し、瞑想と思索によって宇宙自然の大法則(真理・・・ダルマ)に到達することにより悟りの境地に対するとするものであること、さらに、ある一つの立場を堅くとり、他の考え方をあくまで排撃するというような狂信的な態度あるいは排他的な態度をとらず、他と争うことなく寛容である。そしてまた、仏教は慈悲の宗教と言われるようにすべてのものに慈悲をかけるという精神をおりこんだ。西欧の思想とは異種のものであった。
アジアのこうした仏教の教えは、自然のすべての生命を崇拝し、残虐な行為をいましめ、動物を愛護するというものであったので、寺院の周囲には数多くの野生動物が集まってきたという。また、仏教と同じ頃出たジャイナ教はずっと極端なものであった。僧たちは、昆虫のような小動物にも大変な気の使いようで、掃除一つするにも、昆虫の生活を乱すことの無いようほうきの使い方に気を使うというくらいであった。ある時、インドで倉庫の中のネズミを駆除しようという計画があったが、それを支持した西欧人と荷物の中にネズミのための飲み水を残しておこうというほど自然の命を大切にしていた土地の人々の考え方には大きな開きがあったという。
日本では古くは呪術と宗教が未分化な状態であり、シャマニズム的な様式が強くみられ天皇統治の伝統を基礎づける祖先崇拝と自然崇拝が中心であったので、後に仏教が入ってきても深刻な対立はもたらされなかった。また、日本古来からのそうした神道と仏教とが共存できたということは日本人の自然観の背景に大きな位置を占めている。インドのある地方でサルやウシを神聖化しているように日本でも奈良公園のシカは「神鹿」とされていたり、日蓮上人発祥地である千葉県鯛ノ浦のタイ、鎮守の森としての神社、寺の周囲の林などすべてこうした宗教的な思想を土台にしている。
しかしながら思想的背景がこのように対照的であっても、いや、このように対照的であるからなおさらそうなのかもしれないが、残念なことに、こと保護の実績、経験は日本人よりはるかにヨーロッパ諸国の方が長い歴史を持っている。それはなぜなのであろうか。